ホオジロザメ(ホホジロザメ)とはどんな生き物?
ホホジロザメ(頬白鮫、Carcharodon carcharias) は、ネズミザメ目ネズミザメ科ホホジロザメ属に分類されるサメ。本種のみでホホジロザメ属を形成する。別名ホホジロザメ(ホオジロザメ)。- Wikipedia より
“ホオジロザメ” と呼ばれる方が多い様に思われますが、和名からすれば正しくは“ホホジロザメ” になります。
"Great White Shark" (巨大な白いサメ) と呼ばれるのが一般的で、他にも "White Shark"(白ザメ) や、"White Pointer"(ホホジロ) と呼ばれたりします。
ホホジロザメ(ホオジロザメ)は、全世界の熱帯から温帯にかけての海に広く分布していますが、基本的には、日本近海、オーストラリア南側、地中海、南アフリカ、アメリカ沿岸、南アメリカ沿岸まで、大陸沿岸を活動範囲にしています。生物の少ない遠洋ではなく、餌になるアシカやアザラシが多い沿岸近くを活動エリアにしているようです。
当然ながら、人間と出くわす機会も増えてしまいます。
とは言え、映画ではしばしば海水浴客でにぎわうビーチに不気味な三角形の背びれが迫ってくるのですが、実際にはホホジロザメ(ホオジロザメ)はもっと冷たい水温を好みます(12~24度C)ので、あまりビーチには現れません。
ホホジロザメ(ホオジロザメ)に『ヒト食いザメ』のイメージを定着させることになった、スティーブン・スピルバーグ監督の代表作の一つ、映画
『JAWS』 のモデルになっている「人喰いザメ」も、
「体長8m/体重3000kg」のホホジロザメ(ホオジロザメ) という設定になっています。
平均的なホホジロザメ(ホオジロザメ)の体長は、4.0~4.8メートル(トヨタの新型クラウンが、約 4.9メートル)、体重680~1100キログラム(トヨタのカローラが約 1000キログラム) と言われていますが、魚類は生きている限り大きくなり続けますので、それよりもはるかに大きな個体が存在していても不思議ではありませんし、台湾沖やオーストラリア沖などで、推定で体長7メートル以上、体重2500キログラム以上の個体が捕獲されたことがあるといいます。
『JAWS』級の巨体もあながちフィクションとは言えないかもしれません。
ちなみに川崎にある「川崎マリエン」には、平成17年に死んで川崎港に漂着したホホジロザメが剥製として展示されています。“かわジロー”というお茶目な名前が付いていますが、体調 4.85m のオスで、胃の中からはイルカの尾が出てきたそうです。
この1トンを超える巨体が最高速度35km/hのスピードで襲ってきます。
平均的なサイズのホホジロザメ と、大型乗用車トヨタクラウンレベルとのサイズ比較
とは言え、当然オスとメスが出あわなければ子孫ができない訳ですが、これまではランダムに浅い海で餌を探している最中に出会うのでは?程度に考えられていました。 そんな中2009年に興味深い『ホンマでっか?』 な研究結果が報じられました。
「ホオジロザメ」には、お見合いのための「カフェ」がある というのです。
ホホジロザメ(ホオジロザメ)が広範囲に回遊する事は知られていましたが、以外に狭い範囲をコースを決めて季節ごとに回遊していることがわかりました。“ White Shark Cafe' ”「ホオジロザメ・カフェ」 で一服し、メスと交流を図る(ナンパ?)と言うのです。“ナンパ”と言っても、最低でも100日程度は居座るそうですので、かなり気合が入っています。「ホホジロザメにもナンパスポットがある」 というのは十分に信用できる情報かと・・・
ホホジロザメ(ホオジロザメ)の見分け方と特徴
"Great White Shark" (巨大白ザメ)と呼ばれていますが、白いのは腹の部分だけで,背中は多くの他のサメと同様にや黒ずんだ灰色をしています。
まさに弾丸!という体系に巨大な尾びれが特徴的なホホジロザメですが、この尾びれにパワーをおくっているのが、尾びれの付け根の強力な筋肉です。
ホホジロザメの鼻の頭は固く円錐型になっていることもあり、正面から見ると(そんな機会はあまり無いでしょうが・・・)体のわりに口は小さく、さめの下顎の歯が少し覗くだけで、まるで微笑んでいるかの様な顔つきです。
サメの歯はちょうど猫のカギ爪 のように普段は格納しておいて、いざという時には大きくせり出し、アゴも大きく160度も開いて獲物に食らいつきます。
VIDEO
「圧倒的にでかい!三角形の歯」 です。
ホホジロザメの歯の縁にはのこぎりのようなギザギザがついており、かみそりの刃のように鋭く、獲物の肉を引き裂くことができるようになっています。
上あごには、16~20個のノコギリ上の歯が付いた三角形の巨大な歯が並びます。 下あごの歯は小さめでとがった形状でほぼ同じ数が並んでいます。
ホホジロザメは一度かみつくと、下のとがった歯で獲物を固定し、頭を振って上のノコギリの様な歯で切り裂いて引きちぎります。
サメの歯はゾウの牙やサイの角とは異なり、自然に何度でも抜け変わるものです。 ホホジロザメは食餌の際にしばしば歯が抜けてしまったり、餌と一緒にのみこんでしまったりしています。
その上、サメは多くの生き物と異なり、上のアゴと下のアゴの両方を動かしてかみつくことができる極めて珍しい(しかも強力)なアゴの仕組みを持っています。
この歯と顎の力でかみつかれたら・・・と想像すると、何とも恐ろしい気持ちになるのも当然です。
VIDEO
ホホジロザメは人を襲う?
「サメは人を襲う危険な生物か?」・・・ この話題は、しばしば論じられており、サメが人を襲ったという数は「ゾウが人を襲うより数より少ない」とか「雷に打たれるより確率が低い」などと表現されるとおり、実際には「好んで人を襲う事は無い」というのが定説です。
最も良く知られているのが「サメは一滴の血のにおいに集まる」という嗅覚です。
こうしたハンターとしての能力の高さゆえに恐怖心が先に立つかもしれませんが、実は臆病で慎重な性格のため、好んで人に近付いてくることは極めてまれです。
全世界で毎年100件くらい報告される「人間がサメに襲われた」という事件が報道されます。「ヒット・アンド・アウェイ戦法!」
サメが「血のにおいをかぐと凶暴になる!」という話も聞きます。実際にヨゴレ( Oceanic White Tip Shark)やヨシキリザメ(Blue Shark)などは、狂乱索餌(きょうらんさくじ) と呼ばれる、狂乱状態になりながら餌に食らいつく様子が見られます。 これは、海中に多量の血が流れ、獲物が苦しんでもがいていたり、それに突進する仲間のサメなどが立てる音などにより、非常に敏感なサメの感覚器官からの情報が処理能力を超えてしまい、完全にイカレタ状態になってしまう現象です。こうなると、上も下も、仲間だろうが何だろうが見境なく、何にでも手当たり次第にかみつきます。
しかしながら、ホホジロザメの場合には、あまりこの現象は見られないようで・・・なんとかじっくりと様子を見られているすきに逃げだすチャンスがあるようです。
また、ある研究家は『ホホジロザメ(ホオジロザメ)は人間の肉が嫌いだ!』 と主張しています。
現在では、人が襲われたという事例は、ホホジロザメ(ホオジロザメ)による、食べれるかどうかの「試しのひと噛み」 か、サーバーを海の底から見上げたシルエットがアザラシに似ているという「人違い」 であるというのが定説となっています。
実際に「ホホジロザメに食べられた」という話はほとんど聞いたことが無く、一回目の“ひとかみ”攻撃により「重要な器官が損傷した」「出血多量で助からなかった」といおう話がほとんどです。
(まあ、自然界には人間のように「動けなくなった仲間を助けて、水の外に避難させる」様な生き物はいないのですが・・・)
結局人間は脂肪を蓄えたアザラシなどと異なり、「ちょっと噛んでみたけど、骨ばっかりで消化に悪そうだから・・・いらね!」 と言うのがホホジロザメ(ホオジロザメ)側の言い分でしょうか。
有名なオーシャン・ラムジーさんが5mオーバーのホホジロザメの背びれにつかまって泳いでいる動画です。
VIDEO
でも。。。。万が一ホホジロザメに襲われたら?
よく「鼻の頭を殴れ!」 といいますが、たぶんある意味では効果があるのではないでしょうか?
鼻をなでられてサメがしびれたように寝てしまう有名な動画
VIDEO
ちなみにホホジロザメの場合は、鼻先と左右の鼻の穴の中間内側あたりに多数のロレンチニ瓶と言われる1mm前後の小さな孔の集合箇所があり、その辺にを撫でるとしばらくの間しびれたように動かなくなったり、海面を仰向けに泳ぎいで痙攣することもあるそうです。
ロレンチニ器官とは・・・生物が発する微かな生態電流や地球の磁気などを感知し、位置や方角を捉える機能がある。また、地球上の磁場や電界によって、海流・海中生物・金属等も認知する。この特殊な器官によって、暗く見えない夜の海の中でも、遠方から獲物を察知し、正確に捕らえる事ができる。サメの鼻には数種類の感覚受容器が並び、海水温度・海水成分・塩分濃度・川の位置と大きさ・汚染地帯・海底火山の場所・海底地形等も識別している。100万分の1の血液濃度や摂氏1000分の1の海水温の違い、聴覚は数十キロ、嗅覚は数百キロ、視覚は十数メートル先まで解るといいます。
サメは神様?
海の恵みにより生活している多くの海洋民族にとって、漁に出掛けた際に出会うかもしれないサメは恐怖の対象である共に、神聖な存在 として見られていました。
狩猟や漁で生活している人たちは、生活の糧としてあるいは自らの身を守るために、クマやオオカミ、サメやクジラを狩って殺します。
そうした中で、オオカミやサメなどを「山の神」「海の神」 として尊敬したり崇拝したり、その強さの象徴である牙や爪をお守りにするような習慣も生まれてきたのでしょう。
オーストラリアやニュージーランド、ハワイなど、オセアニアの島々においても、サメは漁の安全や航海を守護してくれる海の守り神として敬われています。
ニュージーランドのマオリの間では、特にホホジロザメ(ホオジロザメ)を、"mango-taniwha" (サメの怪神?)と呼んで、畏敬の念を持って扱ってきたそうです。
ハワイ諸島では、19世紀の初めごろまで“サメ崇拝”の習慣があり、島ごとに特定の種類のサメをあがめており、誤って他の島の神聖なサメを殺してしまう事で、しばしば島同士の戦争にまで発展していました。
タヒチ島ではサメを海の神として祭っています。 タヒチ島は元はサメであった という言い伝えもあるくらいです。 その信仰によれば、この鮫は神主命令に従い、船が転覆して人が海に落ちた時も神主だけは襲わず、それどころか神主を背中に乗せて何キロも泳いで助けると考えられています。このサメ神様は信者は食べないそうです。
ハワイのモロカイ島では毎年、サメが魚を沿岸まで追って来たのを見て、人に施しを与える神の魚と考えて、これをサメを神格化したのでしょう。海辺にサメを神として祀った祠を建て、毎年初物を取ってサメ神様に献上していました。
日本のエビス様は、クジラやサメにより魚が追い立てられることで大漁をもたらした事から来たとも言われており、今では鯛を抱えて釣り竿を持った人間で描かれていますが、古来はサメやクジラのイメージでした。伊勢国の磯部大明神は、今でも漁師に重く崇められています。そこではサメを神からの使者として厚く信じており。信者が海に溺れそうなときには、サメがやって来て、背中に背負って陸まで届けると言い伝えられています。
サメがやってくる時には、信心深い漁夫の船に無数の鰹が集まり、それをとらえて金持ちになり、信仰の薄い人の船が近づくとたちまち群れは去っていきます。
日本の古文書の中には“サメ”が神と呼ばれたという記述はありませんが、一方で“ワニ”はしばしば出てきます。有名な『因幡の白ウサギ』をはじめ、『肥前国風土記』『出雲国風土記』などの古書にも海からやってくるワニが神格化されて扱われています。
もちろん日本にワニはいませんので、“ワニザメ”のようなサメを指していると考えるのが一般的です。
ただし日本近海にはあまりホホジロザメはいませんし、サメに関する姿形の描写からしても日本でのサメ崇拝はホホジロザメではなさそうです。
パレスチナの海辺のワニが羊襲うという話がありますが、これも実際にはサメであると考えられています。
太平洋の国だけでなく、東インド諸島やアフリカの海に近い国では、サメをあがめる習慣を持っています。漁師が海に出る時には、サメなどの目に見えない海中に潜んでいる恐怖に対して様々な“まじない”を行って身の安全を願っていました。
海で生きるしかない人々にとって、サメとの遭遇は避けることができません。それでもサメに対する恐怖心を、なんとか克服してサメと共存するためには、単なる恐怖心から神聖なものに対する恐れとして昇華する方法を見出したのでしょう。
ホホジロザメ(ホオジロザメ)の寿命
最近まで、サメの年齢は背骨にできる木の年輪のような輪を数えることで推定し、ホオジロザメの寿命はおよそ20年程度と考えられていました。
米ウッズホール海洋研究所などのチームがつい最近(2014年1月)米科学誌プロスワンに、「体の長さが5メートル近い雄が73歳まで生きた例があった」という新しい研究結果を発表し、話題になりました。
研究者たちはこれまでとは異なる手法として、体内に取り込まれた放射性炭素の量を測定 することで、ホオジロザメの年齢を測定する方式を試してみたそうです。
これは化石の年代測定で行なうようなやり方の事ではなく、1950~1960年代に海上で行なわれた核実験で大気や海に放出された放射性炭素の量は正確なデータがあるため、ホオジロザメの体内に取り込まれた放射性炭素量とそれらのデータを比較することで、ホオジロザメの固体の年齢を測定するという方法です。
ホホジロザメの寿命は人間と変わらない のです。
ホホジロザメの保護
日本人にとっては、サメは漁の邪魔をする厄介もので、「サメを食べる」ために獲る・・・というイメージは一般的では無いと思います。サメを獲るのは、むしろ「サメ退治」というイメージが強いかと思います。
今年(2013年5月)にも、フカヒレ目当ての乱獲で減少が著しいシュモクザメなどのサメを国際的な取引規制の対象とするワシントン条約締約国会議での新たな決定が行われ、日本政府は“シュモクザメの仲間3種とヨゴレとニシネズミザメ”に関しては規制の受け入れを拒否する「留保」の申し立てをしましたが、投票国の3分の2以上が賛成しています。
世界的なサメ保護の動きのなかで、日本でもやがて輸出入が禁止されるようになるかもしれません。


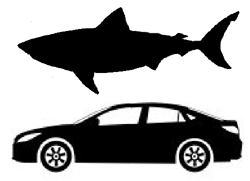









![[表示現品] オオカミ柄ガラスメダル付狼牙ペンダント大 (青) - 15455zhb [表示現品] オオカミ柄ガラスメダル付狼牙ペンダント大 (青) - 15455zhb](https://hf5uftqv.user.webaccel.jp/bmz_cache/t/tibetan_access-15455zhbjpg.image.240x240.jpg)



